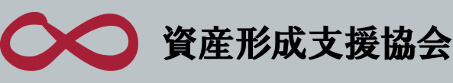2019年にニュースで取り上げられた老後2000万円不足問題が契機となり、「資産運用は怖いというイメージがあり、定期預金にしている」と考えていた方々が、資産運用の必要性を感じ始めています。
実際に、「長期の資産形成のご相談が増えている」と感じている保険代理店は76%にも上ります。
高齢社会の到来を踏まえて、長生きするリスクに備えて資産形成の重要性を認識されているお客様は増えてきています。
「変額保険」や「外貨建て保険」での提案が適切でないかもしれないと思いながら必要のない保障をつけた保険を提案したり、
ほぼボランディアで証券会社の口座開設の方法をレクチャーするなどのリクエストに応えていた募集人の皆様が
「協会に入ってからはお客様に喜んでいただける提案ができるようになり口コミでの紹介も増えた、やりがいを感じながら仕事ができるようになった」
という声をいただくようになり、私共としましてもさらに多くの仲間を増やしていきたいと考えております。
【投信NAVI】が変額保険の販売に役立つ本当の理由
もともと「投信NAVI」は証券会社や銀行等の金融機関による投資信託販売支援を目的に、国内の公募投信のほとんどを掲載することで自社取り扱いの商品にかかわらず公平な目線でファンド選びをしていることをお客様の前で分析結果を証明し、おススメする根拠を示すために開発されました。
弊会では、この「投信NAVI」をお客様本位の提案を志す意識の高いIFAが資産形成のご相談を承った際に、投資信託の提案時に使っていただいています。
さらに、弊会会員様のなかには、「変額保険の提案に「投信NAVI」を使い始めたところ飛躍的に契約率があがりました!」という嬉しいご報告をうけるようになりました。
普通の変額保険提案の場面では、パンフレットに乗っている死亡時の保障額と解約返戻金3%のケース、6%のケースを説明にとどまったりですとか、
特別勘定の説明時に「現在は世界株式インデックスが〇〇パーセントで回ってますよ~」
というトークだけで、契約に進むケースもあるかと思います。
今後起こりうる下落のリスクなどの説明を簡単に済ませてしまい販売すると、不況時に下落した特別勘定がいつ回復するのかとお客様が不安になった場合に説明を求められる場面も来るかもしれません。
そんなとき、あらかじめ過去の○○ショックの時はこれくらいの下落幅があり、回復するまでこれくらいの期間を要し、その後はどのような水準で推移していたのか?
それでも運用を継続すれば長期的には世界経済は右肩上がりであり、大きな資産が形成が見込めるファンドが実在することを
グラフなど視覚的にひとめでわかる説明をすることで、口頭で説明するよりもお客様の納得性を高め、喜んで運用に踏み出す勇気を得ることで、変額保険の契約、iDeCo、NISA等の税制優遇制度を使った運用に踏み出すようになり、未来に希望を持てるようになるきっかけを作ってさし上げることができるようになります。
また、実在の投資信託を例に挙げ、もしあなたが、20年前から〇万円づつこのファンドに積み立てていたら、今、○○〇〇万円になっているんですよ!
このファンドは、20年間で○○%の運用利回りがでていますよ。
と資産形成が現実のものとしてイメージしやすくなるのが「投信NAVI」を使う一番のポイントなのです。
【投信NAVI】で変額保険を販売する場合のポイント
協会では「変額保険」を提案する際に「特別勘定」の中身について説明できるようになることで格段に販売がしやすくなるようサポートしています。
特別勘定を説明する際に、保険会社提供資料以外の資料を使用して説明することはありませんが、募集人が、事前にお客様の金融リテラシーを高める意味で「投信NAVI」を使って実在の投資信託の値動きの特徴やリスク・リターンをご説明することで予備知識を吸収しておいていただくことができます。
そうすると変額保険を提案する際に、特別勘定の選定を後押ししやすくなります。
「投信NAVI」で、特別勘定選択の根拠となる考え方を学んでいただくトーク術を習得していただき、お客様への定期的なご訪問や商品の見直し提案のきっかけづくりにもなります。
変額保険の提案につながるポイントとして特別勘定と近いパフォーマンスの実在するファンドを選び、シミュレーションをお見せするのが有効です。
【特別勘定】と近いパフォーマンスのファンドを分析する際の注意点
投信NAVIで特別勘定の分析をしたいと思っても、該当するファンドの運用期間が短く長期的な分析ができないことがあります。
その場合は、その特別勘定と近いボラティリティのファンドで長期運用しているファンドで代用しシュミレーションするのがポイントです。
〇〇ショックや、○○バブル崩壊などの下落相場を経験してもなお、積立の場合はボラティリティの高い特別勘定を選択する方が長期的には有利であることを実感してもらえます。
なお、外務員資格を持たない募集人が「投信NAVI」を利用する場合はお客様の金融リテラシー向上のための教育ツールとしての位置づけでご使用ください。
実際の変額保険の特別勘定の説明については各保険会社が用意している説明資料を使って説明してください。
また、シミュレーション結果はあくまで実在のファンドの過去の実績であり、その後説明する変額保険の特別勘定の実績とは異なることと、将来の実績を確約するものではない旨のご説明は欠かせません。
特別勘定と近いパフォーマンスの分析につかうファンドの選定についても、会員様へアドバイスさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
「変額頬県の成約率や紹介率が飛躍的に向上するIFA的知識とアドバイス習得セミナー」動画
2022年4-6月:村上氏「変額保険の成約率が上がる IFA的アドバイスセミナー」
■FP(資産形成)相談に応えられず、保険契約に結び付かない経験はありませんか?
■「投信NAVI」システムを使って長期資産形成の大きな可能性を伝えることができれば、 変額保険の提案の仕方が変わり、 多くの生命保険の約定に繋がります!
■続々とIFA化する保険募集人の保険契約成功事例をご紹介!
講師:オールアセットマネジメント 村上様
「特別勘定の分析で覚える投信NAVI」
変額保険で資産形成ができるのか?
変額保険で資産形成提案をしてらっしゃる募集人も実際いらっしゃいます。
しかし、特別勘定と同じマザーファンドで運用しているファンドを投資信託で運用したとしたら
同じ6%で運用できたとしても、解約返戻金は変額保険のほうが20~30%程度劣後することもあり、投資信託での運用をするほうがはるかに資産形成には寄与します。
変額保険は保険関係費用等が差し引かれたうえで、運用されるからです。
最近では、保障部分がほとんどないほぼ全額を運用にまわせる変額保険もありますが、
2024年の税制改革で新NISAが恒久化されることで、より投資信託での運用のほうがメリットが高まり、変額保険での提案は、保障を特別勘定という運用の力を使って、結果的に保障を割安で準備できたり、資産形成ができるかもしれないという色合いでの提案となることが見込まれます。
ただし、変額保険は保障という色合いが強いので、ほとんどの方が10年以内に解約することはありません。
一方、投資信託での運用の場合、購入直後からリーマンショックのような下落相場をたどった場合、不安から売却してしまう可能性が高いのです。
といった意味で、変額保険で結果的に投資信託での運用よりも資産形成ができる可能性はある。
冷静に運用を継続しつづけることができれば投資信託のほうが資産形成ができるということになります。
いずれにしても、一喜一憂することなく、投資信託(特別勘定)を長期で保有(積立)し続けることが資産形成を成功させる肝であることをより多くのお客様へお伝えいただけるアドバイザーになっていただきたいと思います。
関連記事>保険代理店が投資信託を販売するには
関連記事>保険代理店による資産形成提案が必要な理由
関連記事>保険代理店による投信販売サポート状況